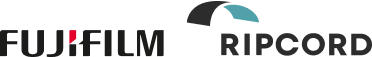-
お客様名渋谷区
-
所在地〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1
-
URL
課題と解決策
- 課題
-
- 職員数の増加や新型コロナ・選挙など臨時の業務対応に伴い、全庁的に不足している執務スペース・会議室の確保
(交流スペース拡充による職員間コミュニケーションの活性化) - 機密性の高い紙文書管理に伴う劣化・盗難・紛失リスクの抑止
- 経年で蓄積され、増大する行政文書の情報参照工数の圧縮
- 職員数の増加や新型コロナ・選挙など臨時の業務対応に伴い、全庁的に不足している執務スペース・会議室の確保
- 解決策
-
- ペーパレス推進体制のプロジェクト化、および各部署が保有する文書の調査~仕分けによるデジタル化対象文書の選定
- 各部署ごとに異なる業務プロセスのヒアリングに基づく文書デジタル化標準仕様の策定
- 紙文書のデジタル化によって保有文書量を削減し、書庫として使用していたスペースを有効活用
- ペーパレス推進体制のプロジェクト化、および各部署が保有する文書の調査~仕分けによるデジタル化対象文書の選定
都内屈指の繁華街でありながら、代々木公園や明治神宮をはじめとする緑豊かな景観にも恵まれた街・渋谷区。この街の戸籍住民登録や証明書の発行などの窓口業務や道路・公園・公共施設などの整備・管理、福祉や教育に関連した相談対応、災害対策などを日々行っている渋谷区役所は、2019年1月の庁舎建て替えによる移転を契機に文書削減に取り組まれていました。
その結果、文書管理システムによる電子決裁の導入や、文書管理ガイドの策定による文書管理のルール化によって紙文書を大きく削減することができたものの、新庁舎移転後も依然として書庫内には多くの紙文書が残っており、さらに職員数の増加に伴い年々庁舎内のスペース不足の問題が深刻化している状態でした。そこで全庁的に紙文書のデジタル化を推進し、庁舎スペースの有効活用に向けて、プロポーザル方式による企画提案の結果、富士フイルムRIPCORDに2022年7月より本プロジェクトの支援をご依頼いただきました。
発注の決め手やプロジェクトへの率直な感想、今後の展望について、渋谷区デジタルサービス部 部長 ICTセンター長(統括課長)事務取扱 伊橋 雄大様、ICT第一係長 山室 俊昭様、総務部 総務課 庁舎管理係
島野 歩様に伺いました。
01 喫緊の課題だった「庁舎内のスペース不足」を紙文書デジタル化によって解決できるパートナーを探していた
ー 富士フイルムRIPCORDに紙文書デジタル化のお問い合わせをいただくまで、渋谷区様はどのような課題をお持ちだったのでしょうか。
山室:2019年1月の新庁舎への移転時に文書課主導で紙文書を約50%削減することができたのですが、移転後は紙文書を減らすという意識が徐々に薄れてしまい、各フロアの書庫に文書が増え続けてしまっていました。さらに、新しい事業部の立ち上げに伴う職員増員や臨時業務などにより、執務スペースや会議室が足りなくなっていたため、「紙文書をデジタル化して書庫をなくし、空いたスペースを有効活用しよう」というプロジェクトを新たに立ち上げることになりました。
(写真中央)「庁舎スペース利活用における文書デジタル化プロジェクト」始動後、プロジェクト推進を担当されている渋谷区ICTセンターの山室 俊昭様
ー 富士フイルムRIPCORDにお問い合わせをいただいた経緯をお聞かせください。
伊橋:そもそものきっかけは、2021年に前副区長が紙文書のデジタル化に関する情報収集をしていた際に富士フイルムRIPCORDさんのホームページを見つけて、国内の金融機関の導入事例や紙文書デジタル化の独自技術に興味を持って問い合わせをしたことが始まりです。後日、来庁いただいた際、私も同席してご挨拶させていただいたのを覚えています。
渋谷区ICTセンターで紙文書ペーパレス化推進のPMOを務める伊橋 雄大様
榎本:副区長様から直々にお問い合わせをいただいたときにはとても驚きました。私は前職で長く自治体様のソリューション提案営業をしてきたのですが、自治体様は実績を重視される傾向があります。富士フイルムRIPCORDとしては、渋谷区様にご相談をいただいた時点では自治体様のご支援実績はありませんでした。しかし、私たちはAIでホチキスの有無を判定し、留められているホチキスをロボットが自動的に除去するなど、紙原本の破損リスクを抑止しつつ大量の文書を効率的にデジタル化できる独自技術を保有しており、行政文書デジタル化のお役に立てるだろうと考えておりました。そのような矢先にお問い合わせをいただきました。
伊橋:来庁いただき、御社のサービスについて紹介いただいてからしばらく間が空いてしまったのですが、その間にも庁舎のスペース不足の問題はさらに深刻化していました。
小笠原:まず最初に、文書をデジタル化することによる効果や価値を具体的にイメージしていただくために、環境政策課の緑化計画書、完了書を対象としたイメージデータ化と生成したデータを有効活用して業務を効率的に実施するためのデジタル環境をご提案させていただきました。
本プロジェクトのサービス設計やプロジェクトマネジメントを担当した富士フイルムRIPCORD セールス&マーケティング部 マネージャーの小笠原 佳幸
ー 情報活用に向けた文書デジタル化の提案をご覧になって、どのような印象を持たれましたか?
伊橋:前副区長は紙文書のデジタル化に非常に意欲的で、当初から「役所の紙をすべて電子化したい」という思いをお持ちの方だったのですが、実を言うと私を含めた他の職員はみんな「本当に紙の業務をデジタルに置き換えることができるんだろうか…」と半信半疑でした。しかし、富士フイルムRIPCORDさんから提案を受け、イメージデータを確認した際に、我々の想像以上に鮮明で、かつ抽出されたデータの精度も高く、業務効率化の可能性も感じることができ、「この技術を活用すれば、書庫スペース削減、業務生産性の向上に向けた業務環境のペーパレス化が実現できるかもしれない」と感じました。このような準備段階を経て、2023年に「庁舎スペース利活用における文書デジタル化業務委託」のプロポーザルを実施することになり、富士フイルムRIPCORDさんにもご参加いただくことになりました。
02 役所特有の文書にフィットしたテクノロジーだけでなく、課題に寄り添う力や文書情報活用まで見据えた提案が選定の決め手に
ー プロポーザルの結果、富士フイルムRIPCORDを本プロジェクトの委託先に選んでいただいた決め手は何だったのでしょうか。
伊橋:プロポーザルには複数社にご参加いただいたのですが、富士フイルムRIPCORDさんは独自のテクノロジーを用いて行政文書を効率的かつ高精度にデジタル化できる技術力が優れていると感じました。さらに、我々が抱えているさまざまな課題に寄り添い、各部署ごとに異なる業務プロセスにも対応できるデジタル化仕様や、デジタル化の先にあるデータの利活用にまで、非常に具体的かつ熱のこもったご提案をしていただけたことが選定の決め手でした。
また、機密性の高い文書が多数あることから、情報紛失リスクや文書の経年劣化による情報消失リスクを低減させることも本プロジェクトの目的のひとつでした。当然ながら委託先のセキュリティ体制は重要な選定基準でしたが、デジタル化センターを視察させていただいた際に、生体認証の導入や文書の導線上にカメラが設置されているなど、厳重なセキュリティ対策を取られていることが確認でき、預け入れる文書の管理面でも優れていると感じました。センターで実際に作業されている様子や、マシンによって紙文書がどのようにスキャンされているか、品質確認の工程なども含めて間近で見ながらデジタル化の各工程をご説明いただいたことが印象に残っています。
本プロジェクトのプロポーザルでは、文書のデジタル化および庁舎スペース利活用に向け、課題の整理から各ステップの具体的な進め方までをご提案
榎本:伊橋様のお話の通り、我々がご提案時に重要なポイントだと思っていたのは、富士フイルムRIPCORDのテクノロジーを使って行政文書を効率的に精度よくデジタル化することだけではありませんでした。渋谷区役所様が全庁的に紙文書のデジタル化を推進するにあたり、どのような課題が起こり得るかを洗い出し、文書の中でも「デジタル化に適するもの」「倉庫に保管しておいた方が良いもの」「処分して問題ないもの」といった仕分け基準を明らかにした上で、「デジタル化する意味のある文書を絞り込む」、そして「文書情報参照の際に検索性の高いデータに変換する」というところがご提案の肝でした。さらに、プランを描いて終わりではなく、実現に向けて実際に我々が並走し、各部署の皆様にもご協力いただきながら全庁を巻き込んでプロジェクトを進めるための「実行支援力」も非常に重要なポイントだと捉え、注力してご提案させていただきました。
(写真左)富士フイルムRIPCORD セールス&マーケティング部 本部長の榎本 喜栄。前職では地方公共団体様向けにシステム導入および業務改善プロジェクトを20年来経験していた
03 全庁を巻き込んだプロジェクトの障壁を乗り越えられたのは、富士フイルムRIPCORDの支援があってこそ
ー 本プロジェクトを渋谷区様が推進されるにあたり、各プロセスにおいて富士フイルムRIPCORDがどのようにお役立ちできたのか、お聞かせください。
山室:各部署が持つ行政文書の棚卸調査、デジタル化の要否、デジタル化後の廃棄・保管などの文書仕分けの支援、ファイル名、フォルダ構成の指定にかかる助言、文書搬出時に参照が必要となった際の短納期デジタル化(優先スキャン)など、ペーパレス化プロジェクトを推進する上で必要な多くのプロセスをサポートしてもらっています。また、新たに発生する紙文書を、継続的にデジタル化する環境の構築についてのご提案もいただいています。
中でも、特に富士フイルムRIPCORDさんにご支援いただいて助かったのは、「業務環境を紙からデジタルに移管するにあたり、本プロジェクトのすべての関与者から理解を得る」というプロジェクトの円滑な推進に必要な意識改革へのサポートでした。
小笠原:文書を搬出する際には各部署に向けて説明会を実施させていただいたのですが、文書のデジタル化に対する意識や考え方はご担当者様によってさまざまでした。「文書搬出からデジタル化までの間に業務に支障はないだろうか」「デジタル上での参照で必要な情報は得られるのだろうか」と不安を感じている方々に対しては、ご担当者様一人ひとりの想いを対話で確認させていただき、懸念点を解消した上でプロジェクトの実行にご協力いただけるよう、個別にご支援させていただきました。
例えば、ある部署の職員様は、「数十年前に作成された図面を広げて土地の権利者の方と打ち合わせをする業務が度々発生する。その図面に書かれた薄い手書きのメモなどがデジタル化された文書では読み取れないのではないか」とご不安な様子だったため、実際の文書をお預かりし、デジタル化センターでスキャンしてサンプルをご覧いただくと共に「古い文書に関してはこれ以上そのまま取っておくと劣化が進むため、デジタル文書として残した方が現状維持できますよ」といったメリットを説明することでご納得いただくことができました。
山室:小笠原様の各種ご支援が円滑なプロジェクトの推進につながっていると思っています。
また、本プロジェクトの推進にあたって懸念していたのは「搬送した文書の閲覧が必要になった場合にどう対応するか」という問題についてでした。しかし、情報参照が必要となった際に対象の紙文書を優先的にデジタル化し、先行して送付いただくという柔軟なご対応をいただくことができたため、業務に支障が起きなかった点は非常に助かりました。
小笠原:渋谷区様のケースでは、単に保管目的でデジタル化するのではなく、実際に庁舎の窓口などで使われている文書が多いという点が特徴的でした。そのため、「この文書をすぐに確認したい」というご要望に対応できる体制を整え、「優先スキャンサービス」として提供させていただいています。具体的には、お預かりしている原本を郵送で返却するのではなく、デジタル化のラインの一番先頭に入れ、即時的に処理を行い、PDFでお返しをするという形でご対応しています。
山室:一度搬出すると約2ヶ月は手元から文書がなくなってしまうため、このサービスは総務課をはじめとする各部署からも「非常に助かっている」という声が上がっています。
島野:私も実際に優先スキャンを頼んだことがあります。役所は業務上、住民から何らかのお問い合わせをいただいた際に、急遽調べなければならない書類が出てきてしまうのですが、優先スキャンをお願いしたい文書をお伝えすれば翌営業日にはご用意いただくことができ、とても助かりました。
04 ペーパレス化に向けた業務サイクルの構築や庁外施設への横展開の支援にも期待
ー 本プロジェクトの現在のご状況についてお聞かせください。
山室:本庁舎における既存文書の電子化は2025年度の完了に向けて進行中ですが、富士フイルムRIPCORDさんのご支援のおかげでプロジェクトは順調に進んでいます。
各部署一斉に文書の梱包などの作業を実施するため、繁忙期と重なるなどの理由で当初計画のスケジュールに間に合わないというケースがいくつかありましたが、搬出のタイミングをずらしたり、細かく分割するなど柔軟に対応いただき、それ以外の場面でも各部署の負担を軽減するためのご提案をいただくことが多く、助かっています。
プロジェクトは大きく3つのフェーズに分けて進行中
ー 富士フイルムRIPCORDの支援により、どのような成果があったかお聞かせください。
小笠原:プロジェクト開始当初の調査によると、本庁舎に存在する紙文書の枚数は約2,018万枚あり、そのうちフェーズ2でデジタル化対象となった先行フロアには約439万枚の紙文書がありました。当社が文書仕分け・デジタル化をご支援させていただいたことで、令和5年度は約221万枚を廃棄、約182万枚を倉庫に移動し、デジタル化の必要な紙文書については約111万枚のデジタル化が完了しました。
令和6年度も継続して複数フロア単位での文書仕分け・搬出・デジタル化が進行しており、本年度末にはプロジェクト完了予定
山室:富士フイルムRIPCORDさんに仕分け基準を明確化していただき、各部署が保有する文書の調査をしてもらった結果、そもそもデジタル化してデータを保管する必要もなく、即廃棄することができる文書が予想以上に多くありました。本プロジェクトに取り組んだことによって、「無駄な文書を残しておかない」という職員一人ひとりの文書削減に関する意識が高くなったのではないかと感じています。また、紙文書をデジタルに変換したことで、文書情報参照の際の工数削減や、業務効率化についても期待しています。
島野:プロジェクトが動き出すまでは、実際のところどれぐらいの文書量を削減できるのかイメージがついていませんでしたが、フェーズ2において庁舎10階でデジタル化を実施した結果、書庫だったスペースを一室まるごと空けることができました。プロジェクトが動き出したのは2023年4月からでしたが、文書仕分け・搬出が完了したのはわずか2ヶ月後。さらにデジタル化も7月には完了していて、そのスピード感には驚かされましたね。想像以上のスピードだったため、スペースの利活用方法の検討・実施が遅れないよう追いついていくのに必死でした(笑)。
(写真右)文書デジタル化によって確保したスペースの活用方法の検討や実行を推進している島野 歩様
文書デジタル化によって削減した10階のスペースは、外部の方々の出入りが多い点と、全庁舎的に会議・打ち合わせをするスペースが足りないという声が上がっていたことから、広い会議室として活用することにしました。また、10階に続いて文書のデジタル化が完了した7階については、職員数が増えて昼食をとったり休憩中にくつろぐためのスペースが足りなくなっていたため、ワークラウンジに転用できるように改修工事に向けた準備を進めています。
紙文書の削減によって約550㎡のスペースを削減(テニスコート2面分以上に相当)
ー 今後の展望についてお聞かせください。
島野:スペースの利活用については、現在残りのフロアの紙文書のデジタル化によって空いた書庫スペースをどんな場所にしていきたいか、職員にアンケートを取り、ニーズに即したスペースを検討中です。
山室:渋谷区では別プロジェクトで各種手続きのオンライン化推進により紙文書の発生を抑えていく取り組みを進めています。完全に紙の発生をゼロとすることは難しいため、抑止した上で、なお発生する紙文書をデジタル化し、原本を廃棄する…といった継続的なペーパレス化サイクルの構築を目指していきたいと考えています。
また、現副区長は本プロジェクトの成果を高く評価しており、本庁だけでなく区内10箇所にある出張所や、渋谷区が管理している各施設にも展開していきたいという意向があり、実行に向けて富士フイルムRIPCORDさんと協議を進めています。
小笠原:当社は本プロジェクトによってデジタル化を実行して終わりではなく、渋谷区様の幅広い業務の実態に即して最適な選択肢をご提示することによって本当に意味のあるデジタル化支援を行っていきたいと考えています。全庁への展開完了後も、引き続き新たな紙文書の発生の抑止に向けたご支援や、庁外施設の文書デジタル化の推進に向けたご提案をさせていただきたいと思っています。
伊橋:インタビューの冒頭でも少し触れた通り、前副区長はかねがね「『紙』の存在は役所にとって一番のリスク。盗難・紛失・劣化のおそれがある上、文書を探索するのにも毎回時間がかかるので、すべてデジタル化して紙が全くない役所を作ってほしい」という話をされていました。当時は誰も実現できるとは思っていませんでしたが、富士フイルムRIPCORDさんのご支援によってそれが絵空事ではないと思えるようになっていますし、ぜひ今後も「紙の存在しない役所」の実現に向けてご支援をいただけたらと思っています。その上で、他の自治体にもペーパレス化の取り組みが広がっていくことを期待しています。
(写真中央から右)渋谷区 伊橋様・山室様・島野様、(写真左から)富士フイルムRIPCORD 榎本・小笠原